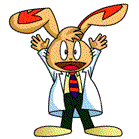| 1.研究内容のご紹介……細胞毒性試験 |
弊社で行っている細胞毒性試験は、ヒトまたは哺乳類の培養細胞に医用材料及び化学物質等の検体を処理し、細胞の生存率から素材が持つ毒性の程度を細胞レベルで判断する試験です。この試験は1995年7月、厚生省(現 厚生労働省)から告示された「医療用具及び医用材料の基本的な生物学的試験のガイドライン」にも損傷皮膚に接触しない体外器具を除くすべての医療用具に必要な試験として取り入れられています。また、このガイドラインはISO/TC194の検討に基づいて制定された各種生物学的評価に関連した国際基準を反映しています。 従来の動物を用いた生物学的試験や化学的な試験では問題がないと考えられていた材料でも、細胞毒性試験によっては毒性が認められる場合があり、この試験の併用によって毒性の強弱が判定出来ることから、より毒性が低く安全性の高い医用材料を選択することが出来ます。PL法施行後、材料メーカーは医用材料の供給に非常に敏感な反応を示していますが、材料メーカーが安心して材料を供給出来るような環境作りのためにも安全性試験の充実は欠かせません。一例をあげれば、以前マスコミ等でも問題になった注射針に使用されるシリコーンオイルの基準にも、細胞毒性試験による安全性確保が定められています。 また、動物愛護の立場からも細胞を用いた試験がますます重要になってきており、弊社では、細胞培養技術を用いての動物実験代替法にも取り組んでいます。個体差の大きい動物実験に比べ、細胞培養による試験は再現性もよく、薬物の一次スクリーニングには適しています。とはいってもガイドラインに基づいた細胞毒性試験であっても実験条件によって毒性の発現に違いが認められており、素材や使用条件を考慮した実験条件が必要となる場合もあります。その一部について、日本動物実験代替法学会において発表を行いました。動物実験を完全に代替するにはまだまだ難しい部分が多く、全てをin vitroの試験で置き換えるというわけにはいきませんが、日本動物実験代替法学会では様々な試みがされており、中でもウサギ眼刺激性試験(ドレイズ法)の代替法に関してはかなりの検討がされています。我々もそのバリデーションスタディに参加致しました。その他、医療機関との共同研究も推進し、その成果が日本新生児学会等で発表されています。 今後、研究・発表を重ねながら組織培養技術の向上に努め、自社製品の安全性試験だけでなく、医療をサポートするための生物学的研究の充実を図っていきたいと考えております。 |