�i���j�����d�@���쏊�@���f�B�J�����Y�{���@�Z�p���@�����w������
�m�ړI�n �@��×p��y�ш�p�ޗ��̐����w�I�����̃K�C�h���C�������N�V���ɐ����ɒ�߂�ꂽ���A���̓��e�̍זE�Ő������͑S�ĂɕK�{�̎����ƂȂ��Ă���A��p�ޗ��̈��S�����l�@�����ŏd�v�Ȉʒu�t���Ƃ���Ă���B���̍זE�Ő������͎g�p�זE����|�n�A�������@�ȂǍו��ɂ킽��ڍׂɒ�߂��Ă��邪�A���̒��Ŕ|�n�ɂ��ẮA�������������|�n����߂��Ă���B�����͔|�{�זE�̑��B���ɐ[���ւ���Ă��邪�A�Ő��������ɂ����ĕs�m���ȗv�f�ł͂���B�K�C�h���C���ɂ����āA�K��O�̔|�n��p���Ă̎����y�шقȂ鎎���@��p�����������s�����Ƃ́A�\�ł͂��邪�A���̎����̐������́A�W���ޗ��������������ʂ��A��߂�ꂽ�����Ɠ����ȏ�̊��x�y�эČ������m�F���ꂤ�邩�ǂ����Ŕ��f�����B�����R���̌����𒊏o���ɗp���邱�Ƃ́A���̂ɂ��߂������Ŏ������s�����Ƃł���A���ɏd�v�ł͂��邪�A�����R���̕������Ȃ�����Ӗ��ɉ����Ă��A�������|�n�ł̎������\�ł��邩��T��Ȃ���A��p�ޗ��̍זE�Ő������i���ɒ��o�����j�ɂ����錌���̑��݂̏d�v���𖾂炩�ɂ���ړI�ŁA�������|�n�ƌ�������|�n�Ƃ̓Ő��������ʂ̔�r���s�����B�܂��A�������@�ɂ��ẮA�R���j�[�@����߂ �m�ޗ��ƕ��@�n �@PTFE�i�|���e�g���t���I���G�`�����j�`���[�u�APVC�i�|�������r�j���j�`���[�u�APU�i�|���E���^���j�`���[�u�A�n���_�iSn-Pb�j�y�щA���ޗ��i�a���g�D�|�{�p�v���X�`�b�N�V�[�g�j�������ޗ��Ƃ��A�W�������@Zincdiethylditiocarbamate (ZDEC), zinc dibutylditiocarbamate(ZDBC) �̍זE�Ő������������ɍs�����B����K�C�h���C���ɒ�߂�ꂽ�W���ޗ��i0.1��ZDEC�ܗL�|���E���^���t�B�����y��0.25��ZDBC�ܗL�|���E���^���t�B�����j�͓���o���Ȃ������B�i���N�S���ɂȂ�Ȃ��Ɣ̔�����Ȃ��Ƃ̂��Ɓj�������אA�ŋۂ�����1g�ɑ��A10ml�̊����Ŕ|�{�t�������A37��CO�Q�C���L���x�[�^�[����24���Ԓ��o����B���o����|�{�t�́E�l�d�l�{FBS5���i�l�n�T�j�|�n�E�l�d�l�i�����Ȃ��j�|�n�A�E�`�r�e301�|�n�i���̑f�j�̂R��ނ�p�����B���o��A���������l�d�l�|�n�ɂ́A�T���e�a�r��������B�e���o�t��K���Ȕ{���Ɋ�߂��āAV79�זE��100�A������60mm�V���[���ɉ����A�R���j�[�@�ɂčזE�Ő��������s�����B�X�ɁAPVC�ɂ��ẮA���o�|�{�t�̌����Z�x���O���A�P����R���A�T���ł��ꂼ�ꒊ�o���A���o�t�����Z�x�ƍזE�Ő��Ƃ̑����ɂ��Ă����ׂ��B�܂��A�l�n�T�|�n�ł̒��o�t�ɂ��ẮA96�E�G���}�C�N���v���[�g�ɍזE�A�����ݐ����S�~103cells/well�y�тP�~10�Rcells/well�̂Q��ނ�p�ӂ��A24����37��CO�Q�C���L���x�[�^�[�Ŕ|�{��A���ꂼ��ɂ��Č��̏������Ԃ�48���ԁA72���ԁA96���ԂƂ��A�j���[�g�������b�h�@�Ŏ����� �m���ʂ���эl�@�n �@���������ޗ��̂����APTFE�����PU�͒�Ő��ł��������߁A���o�|�n�ɂ��Ő����ʂ̍��͕\��Ȃ�������(Fig.1,Fig.3)�APVC�ɂ��Ă͖��炩�Ɍ�������l�n�T�|�n�Œ��o�������̂̕������ɔ�ׁA�����זE�Ő����������B(Fig.�Q)�B�܂��A�n���_�ɂ��ẮA�������|�n(ASF301)�Œ��o�A�|�{�������̂����ɔ�ׂċɒ[�ɋ����Ő����������B(Fig.4)�B�X�ɁA���o�|�{�t�̌����Z�x�ʂɍזE�Ő����r���������ɉ����ẮA�����Z�x�������Ȃ�ɂ��������āA�זE�Ő��������Ȃ�Ƃ������ʂ�����ꂽ(Fig.5)�B����́A�ޗ����o�����ɂ����錌���̑��݂��A��Ϗd�v�ł��邱�Ƃ������Ă���A���ɍ����q�ޗ��̂悤�ɁA�L�@�n�̃��m�}�[��Y���������݂���ޗ��ɂ��ẮA�����̗L�ŕ������n�o���邽�߂ɂ͖������܂ތ����̑��݂��L�[�|�C���g�ɂȂ邱�Ƃ������o����B����A�W��������p���Ăl�d�l�{�T���e�a�r�Ƃ`�r�e�R�O�P�ɂ�����זE�Ő����r�����Ƃ���A�`�r�e�R�O�P�|�n�̕����ALD50�l�ɂ������āA�Q�{���x�����������ʂƂȂ���(Fig.6,Fig.7)���A�n���_�̎������ʂł́A�Q�̔|�{�t�ɂ�����זE�Ő��̍��́A���̌��ʈȏ�ł������B���̌��ʂ��l�@����ƁA�����ޗ��ɂ����ẮA�n�o�������� �@�܂��A�j���[�g�������b�h�@�́A�R���j�[�@�Ƃقړ����̌��ʂ�����ꂽ�Ɣ��f�o���邪(Fig.8�`Fig.13)�A�A�����ݍזE�������Ȃ��Ƃ�����ڗ����A�A�����ݍזE��������������A�������Ԃ������Ȃ�ΓŐ���������ɂ����Ȃ�X��������A�œK�ȏ����ōs���K�v������ƍl������B �@������ɂ���A�W���ޗ���p���������ɉ����čēx�l�@���K�v�ł��邪�A�����ޗ���g�p�זE�A�|�{�t�����ꂼ��̓����𗝉�������ōזE�Ő����ʂf�A�l�@���邱�Ƃ��d�v�ƂȂ�B �i����p���������ޗ��͂����܂Ŏ����p�ł���A���ۂɈ�×p��Ɏg���Ă���ޗ��Ƃ͌���܂���B�j | |
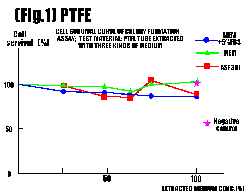 |
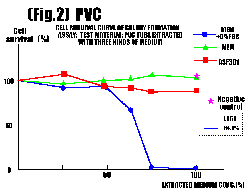 |
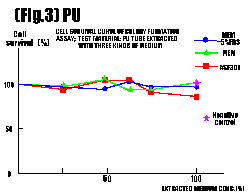 |
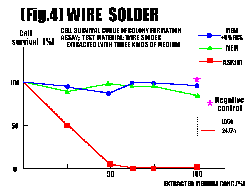 |
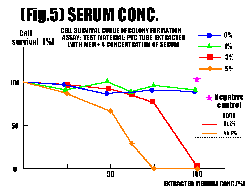 |
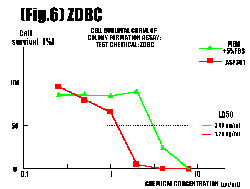 |
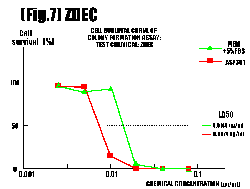 |
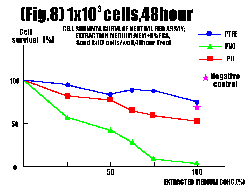 |
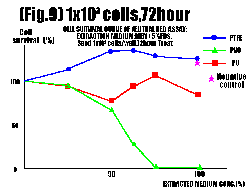 |
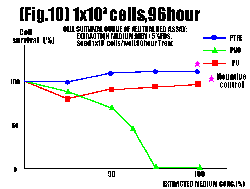 |
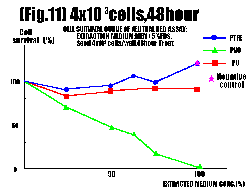 |
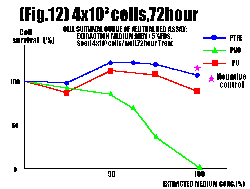 |
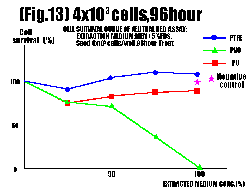 |
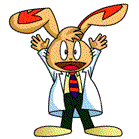 |